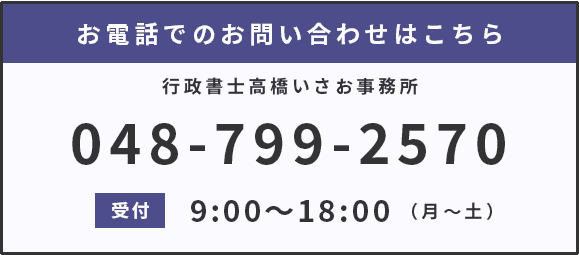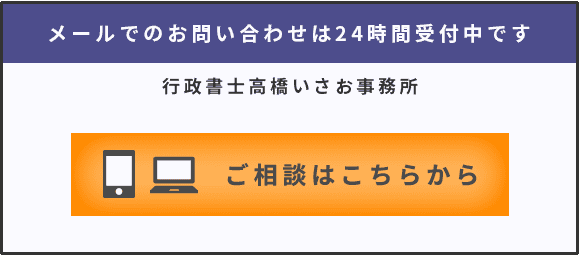運送業(トラック)の許可をとりたいのだけれど、なにから準備すればいいかわからなくて困ってるんですが・・・

一般貨物自動車運送事業の許可ですね?これは関係する法律も多く、要件(許可を受けるのに必要なこと)も多岐にわたり難易度が高い許可申請です。今の準備状況はいかがでしょうか?

まず、営業所は自宅を考えています。トラック5台と車庫の用地は用意することはできそうですが、他にも必要なことが色々ありますよね?

はい、トラック5台にみあうドライバー5人はもちろんですが、運行管理者、整備管理者も必要ですね。車庫の場所や広さにもキマリがありますよ。資金もルールに従って準備しないといけません。
以上は一例です。他にも、ヒト・モノ・カネの3要素について要件(許可を受けるために必要なこと)がいくつも決められています。法令試験に合格が必要、という他の許認可にない要件もありますよ。
このページでは、運送業の許可要件について一通りつかめるように解説しています。個別要件の詳しい解説へのリンクもありますので、まずはこのページで許可の全体像を把握してみてはいかがでしょうか?
(その上でわからないことなどは、文末の連絡先へご遠慮なくお問合せ下さい)
運送業許可とは
貨物自動車運送事業法では、「一般貨物自動車運送」「特定貨物自動車運送」「貨物軽自動車運送」の3種類の事業を定めています。(参考:3種類の「貨物自動車運送業」についての概要はコチラ)。
”特定貨物自動車運送”は、単一荷主の荷物を運送する場合の許可で、許可要件はほぼ「一般」と同じです。”貨物軽自動車運送”はいわゆる黒ナンバーというもので許可制ではなく「届出制」となっています。
以上のように、”運送業許可”といえば、主に一般貨物自動車運送事業を行うための許可ということになりますので、以下はこれについての解説となっています。では、順に確認していきましょう。
許可要件
一般貨物自動車運送事業は国土交通大臣の許可制で、人的要件(ヒト)、物的要件(モノ)、財産的要件(おカネ)に関して定められた要件を満たさなければなりません。
では、ヒトに関する要件から順に確認していきましょう。
人的要件(ヒトに関すること)
- 申請者や会社の役員が欠格要件に該当しないこと
懲役などの一定の刑罰を受けた後、または貨物自動車運送事業法関連の許可取消し処分を受けた後などに一定の期間が経過していない場合など、欠格事由に該当すると許可を受けることができません。 - 担当の常勤役員が法令試験に合格すること
許可申請後に運送事業に専従する常勤役員が、地方運輸局が実施する法令試験に合格しなければなりません。1許可申請当たり2回まで受験可能で、2回で合格できないと申請却下または取下げとなります。 - 必要な有資格者を配置すること
営業所ごとに、有資格者である「運行管理者」、「整備管理者」を定められた人数配置しなければなりません。 - 必要な人数の運転者を選任すること
通常、トラックなどの自動車が最低5両必要なので、運転者も5名以上必要になります。
*運行管理者、整備管理者、運転者は許可申請時点では実際に確保・選任済みでなくとも、確保予定で申請可能です。
以上は要約です。ヒトに関する要件をより詳しく知るには以下のページをどうぞ。
さらに、個別の要件(役員法令試験、運行管理者、整備管理者)のそれぞれの詳しい解説は下記をご参照ください。
物的要件(モノや設備に関すること)
- 【営業所】:適法に設置された、使用権原のある適切な規模のもの
- 農地法や都市計画法、建築基準法などに抵触していない営業所が必要です。例えば、「〇〇住居専用地域」の用途地域には原則として営業所は設けられないことなどに注意が必要です。
- 【休憩・睡眠施設】
- 営業所または車庫に併設することが必要です(睡眠施設は睡眠を与える必要がある場合に設置が必要で、この場合一人当たりの面積基準あり)。
- 【車庫】:営業所に併設または一定の距離内に、全車両が収容できるxもの
- 原則は営業所に併設します。敷地境界と車両、車両相互間にそれぞれ0.5m間隔をとって、全車両が収容可能な広さ(面積)が必要です。
- 営業所に併設できない場合は、営業所から一定の距離内に車庫を設置しなければなりません。
(一定の距離=営業所の場所基準で、埼玉県の場合10km、東京23区・横浜市・川崎市は20km) - 車庫前面道路は、車両制限令に照らして収容車両の通行ができる幅員が必要
- 【車両(トラック)】:必要な数の(通常5台以上)の事業用自動車
- 通常はトラックなど5両以上が必要です(普通自動車で、用途が「貨物」のもの。軽自動車は不可)
- 霊柩運送、一般廃棄物運送、需要の少ない島しょ部などでは、車両1台でOKなどの緩和措置があります。
モノに関して、さらに詳しい解説は下のページでどうぞ。
農地法・都市計画法・建築基準法等に抵触しないことについては 「運送業 事業用不動産の条件とは?」に詳しく書いていますので、ご参考ください。
財産的要件(おカネに関すること)
- 事業開始に要する資金(=所用資金)の見積り
- 役員、従業員の給与・賞与等の人件費や福利厚生費6カ月分、燃料・油脂費など6カ月分、車両費や設備(営業所・車庫等)は賃借なら1年分、新規購入なら購入費全額・・・など、運送事業に必要な経費を所定の様式に基づき積算して見積ります。
- 所要資金の常時確保
- 1で見積もった所要資金の全額を申請時から許可まで「常時確保」することが必要です。通常は、預貯金の残高証明書を許可申請時に提出し、許可が出る前の役所の指示で2回目の残高証明の提出を行います。
- 賠償能力
- 原則、対人賠償無制限、対物賠償200万円以上の任意保険に加入する必要があります。自賠責と任意保険料は、上記の事業開始に要する資金の見積りに算入します。
おカネに関する要件の詳細は 財産的要件をくわしく をご参照ください。所要資金の見積り方の内訳も詳しく解説しています。
許可申請について
許可要件が理解できたら、許可申請の概要(必要書類や手続きの流れ)を確認しましょう。以下の別ページへのリンクから、それぞれの項目をご参照ください。
まとめ
以上、一般貨物自動車運送事業の許可申請について、満たすべき要件を説明してきましたが、複雑な要件、必要な書類の多さなど、新規許可を受ける手続きの負担の大きさをお感じになったのではないでしょうか?
弊所では、新規に一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする事業者様が、営業開始に向け、また営業開始後の事業発展に向け事業プランの策定や実行に注力できるよう、許可要件への対応のご相談に応じつつ、必要な書類の作成、収集と申請手続きを事業者様に代わって行いますので、ご活用をご検討ください。