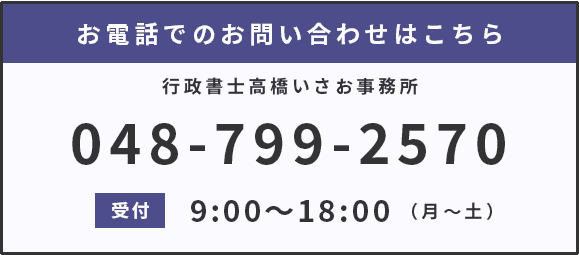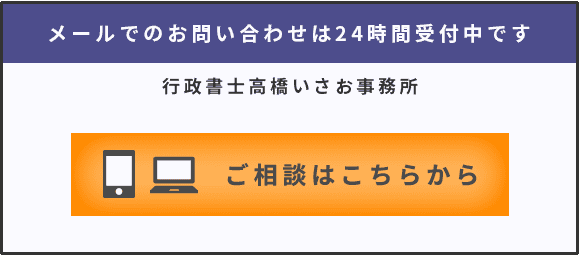運送業(貨物自動車運送事業)を経営していく上では、法令に基づいて備えておかなければならない帳票類が多数あります。これらは、単に書類として作成するだけでなく、実際に記載項目に基づいて安全管理などを行い、その記録を定められた期間保管するとともに、自社の安全運行向上に活かしていくことが大切です。
当サイトでは、多くある運送業の法定帳票類のうち、最も基本となる5種類の帳票について、基本的な記載方法や活用の仕方などを前編・後編の2編に分けてわかりやすく解説していきます。このページではまず、運転者台帳と点呼記録簿を取り上げます。
基本の5帳票
この記事で「基本の5帳票」とは次の5種類の法定帳票を指しています。
- 運転者台帳
- 点呼記録簿
- 運転日報(乗務記録)
- 教育実施計画・運転者指導記録
- 点検整備記録簿(3カ月点検)
それでは、最初に運手者台帳、続いて点呼記録簿を見ていきましょう。
運転者台帳
まず最初は、運転者台帳です。(書式例 : 広島県トラック協会ー運転者台帳)
運送事業者は、「事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならない」とされており、また常時選任する運転者について運転者台帳を作成し管理することが義務付けられています。
運転者台帳作成・管理のポイント
運転者台帳は・・・
- 運転者ごとに(ひとりづつ)作成します。
- 法定8項目の記載と写真の貼付は必須です。
- 作成した運転者台帳は、その所属する営業所に備えておきます。
- 退職などで運転者でなくなった場合はその理由を記して3年間保管が必要です。
必須記載の8項目とは
以下の8項目は法定項目なので、必ず記載しておくことが必要です。
運転者台帳の法定記載8項目
- 作成番号および作成年月日
- 事業者の氏名・名称
- 運転者の氏名、生年月日
- 雇入れの年月日および運転者に選任された年月日日
- 道路交通法に規定する運手免許に関する以下の事項
- 事故を起こした場合、交通違反通知を受けた場合はその概要
- 運転者の健康状態
- 運転者への指導実施の状況、適正診断の記録
8項目 書き方の要点
- 作成番号および作成年月日
・作成番号は、個々の運転者に固有の番号を割り振るようにします。 - 事業者の氏名・名称
- 運転者の氏名、生年月日
- 雇入れの年月日および運転者に選任された年月日日
・運転者に選任された年月日は通常、雇入れの年月日より後の日付になりますので注意しましょう。雇入れてから初任診断や初任教育などを経て運転者に選任するためです。その教育等の期間分だけ運転者に選任した日付が後になります。 - 道路交通法に規定する運手免許に関する以下の事項
・運転免許証番号および有効期限
・運転免許の年月日および種類
・運転免許に条件がついる場合はその条件 - 事故を起こした場合、交通違反通知を受けた場合はその概要
・ここでいう交通事故とは、「人の死傷、物の損壊を生じたもの」および自動車事故報告規則に定める事故(例:自動車の転覆・転落・火災、鉄道との接触、負傷者10名以上の事故‥‥など)
参考: 対象の事故(自動車事故報告規則第2条に定めるもの)
・交通違反通知とは、運転者の交通違反が、使用者(運送事業者)の業務に関してなされたと認めるとき、公安委員会が使用者等に違反内容を通知するもの。 - 運転者の健康状態
・法定健康診断の個人票や、健康診断結果通知書の写しなどを添付するとよいでしょう。 - 運転者への指導実施の状況、適正診断の記録
・事故惹起、初任、高齢の3区分の特定運転者に対する特別指導の内容と、適性診断の結果について記録します。
運転者の写真の貼付
必須記載項目以外で忘れてはいけないのが、運転者の写真の貼付です。
・運転者台帳作成の前6カ月以内に撮影した写真(上3分身、無帽、正面、無背景のもの)を貼付します。
・運転者の写真は、何年かごとに新しいものに貼り替えるといった義務はありませんが、免許に関する事項の記載と写真の貼付に替えて、運手免許証の写しを貼付する方式にして、免許証更新の都度新しいものに貼り替えていく、といった方法をとっても良いかと思います。
(参考)新に運転者(ドライバー)を採用、選任する手順は…
点呼記録簿
事業者は、乗務前と乗務後(必要な場合、乗務の途中)に、運転者に対して「対面で」点呼を行い、必要事項を点呼記録簿に記載して「1年間」保存しなければなりません。点呼で確認する内容も、法令に定められているので、それに基づいて実施し、正しく記録を残すようにしましょう。
(書式例は : 広島県トラック協会ー点呼記録簿)
点呼実施のポイント
●点呼は営業所で行う(原則)。営業所と車庫が離れている場合、運行管理者または補助者が車庫へ出向して行うことはOK。
●点呼は(運行管理の)補助者が行うことができるが、総回数の1/3以上は運行管理者がおこなわなければならない。
●「運行上やむを得ない場合」には、“対面以外の方法”で行うことができる
対面以外の方法で行える場合とは
対面以外の方法で点呼を行えるのは・・・「運行上やむを得ない」場合です。事業者の都合による場合に対面以外でよいというキマリはありませんので、注意しましょう。
対面以外の点呼として正しいのは?
- 乗務が遠隔地で開始、または終了する場合に、携帯電話と車両に備えたアルコール検知器を用いて点呼を行った …〇
- 車庫が営業所から離れているので、携帯電話で点呼を行った …×
- 夜間運行をおこなっているが、夜間は運行管理者が出勤していなので電話点呼を行った …×
- 泊り運行の運転者の乗務開始時にメール連絡により点呼とした・・・×
①は「運行上やむを得ない」場合に該当しますが、②③は事業者の都合であり「運行上やむを得ない」場合には該当しません。
上記の④は、遠隔地で乗務が開始されるので、「運行上やむを得ない」場合には該当します。しかし、対面以外の方法は”電話その他の方法”と定められており、電話や業務無線などのように、点呼実施者と運転者が直接「対話」できる手段であることが必要なのです。
直接対話が必要な理由は、アルコールを帯びていないか、などを確認することが求められるからです。したがって、メールやファクスなどでは必要な確認ができないので、対面以外の点呼方法としては認められません。
点呼の種類(実施時期)
点呼には、実施の時期(タイミング)により、乗務前、乗務後、中間点呼の3種類があります。乗務前と乗務後は文字通りの解釈でOKですが、中間点呼はどのような場合に必要でしょうか?
中間点子は、「乗務前点呼、乗務後点呼の両方とも対面で行えない場合」に必要な点呼です。どちらか一方が対面で行えない場合は該当しない点に注意してください。
例えば、2泊3日運行の場合は、2日目は一泊した場所で乗務開始し、二泊目の宿泊地で乗務終了するため、乗務前点呼と乗務後点呼ともに電話等での点呼となります。
このような場合には、乗務前・乗務後点呼の他に電話等により中間点呼を行わなければなりません(ちなみに、このような運行の場合、運行指示書も必要になります)。
点呼の確認事項と記録簿の記載内容
例えば、運転者が睡眠不足かどうかは乗務前点呼では重要ですが、乗務後点呼では重要ではありませんね。一方、アルコールチェックは乗務中に飲酒していないことを確認する意味で乗務後の検査もたいへん重要です。
このように、点呼の種類(実施タイミング)ごとにチェック内容は決められており、点呼記録簿はその内容を正しく記録しなければなりません。
| 記載内容 | 乗務前点呼 | 乗務後点呼 | 中間点呼 |
|---|---|---|---|
| 点呼執行者名、運転者名 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 乗務する車両のナンバー・番号等 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 点呼日時 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 点呼方法① アルコール検知器使用の有無 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 点呼方法② 非対面の場合、具体的方法 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 酒気帯びの有無 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況 | 〇 | 〇 | |
| 日常点検の状況 | 〇 | ||
| 指示事項 | 〇 | 〇 | |
| 自動車、道路および運行の状況 | 〇 | ||
| 交替運転者に対する通告 | 〇 | ||
| その他必要な事項 | 〇 | 〇 | 〇 |
酒気帯びの確認とアルコール検知器について
酒気帯び運転は重大な結果に直結するため、その有無の確認は確実に実施なければならないので、以下の2点について注意して行うことが必要です。
アルコール検知器を常時有効に保持して備え置く
アルコール検知器は、「営業所ごとに(営業所に属する車両に設置するものを含む)」、「常時有効に保持」して備え置かなければなりません。”常時有効に保持”、とは常に正常に作動し故障がない状態で保持しておくことです。絶対に故障しない機械はないので、基本的には2台以上を備えておく方が良いでしょう。
また以下のように定期的に確認しなければなりません(貨物自動車運送事業安全規則の解釈及び運用について)
- 毎日確認すべき事項
・アルコール検知器の電源が確実に入ること
・アルコール検知器に損傷がないこと - 少なくとも1週間に一度以上(毎日が望ましい)確認すべきこと
・確実に酒気を帯びていないものが使用した場合にアルコールを検知しないこと
・アルコールを含有する洗口液、液体歯磨きなどを口内に噴霧(スプレー)した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。
運転者の酒気帯びの有無について目視等で確認
酒気帯びの有無は、検知器だけでなく「目視」で確認することが必要です。”目視で確認”とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を確認することです。電話等で可とされる点呼の場合、顔色や呼気の臭いはチェックできませんが、声の調子、話し方等でしっかり確認しましょう。
このページでは、基本5帳票のうち運転者台帳と点呼記録簿について、解説しました。残り3帳票(運転日報、教育実施計画・運転者指導記録簿、定期点検記録簿)については、後編で解説していますので、ご参照ください。
当事務所では、法定帳票の整備をはじめ、コンプライアンス向上、安全運行強化をお考えの貨物自動車運送事業者様へのサポートを行っております。これらをご検討でしたら、ぜひお気軽にご相談下さい。

-e1654483470462.jpg)